


『MILBON DA GRAND-PRIX』の第2部AWARDは東京ミッドタウン内ビルボードライブ東京での表彰式。
誰とでも懇談できるようにスタンディングパーティ形式となっていた。
DA OF THE YEARに輝いたのは?そこには感動の結末が待っていた!
コンテストは写真撮影を含め、14時30分に終了した。表彰式は18時。東京ミッドタウンのビルボードライブ東京にて行われる。しばらく時間が空くわけだが、その間に採点の集計がなされ、優勝者が決定する。もちろんこの時点では、出場者には結果を通知されることはない。アワードで初めて知るのだ。
ビルボードライブ東京といえば、ジャズ、R&B、ロックなど、トップアーティストたちがライブを行うことでも有名な場所。そんな高尚な会場でヘアコンテストの表彰式が行われること自体、珍しいことである。

ドアオープンは17時から。エレベーターで4Fへと上がり、薄暗がりの通路を歩いていく。その終着点に扉があり、開けるとシアター型のライブハウスが現れる。ここは3層構造だ。最下層にステージがあり、スタンディングスペースとシート席がある。中間層には音楽や映像を流す機器が置いてあり、演出の要ともいえる場所だ。
最上層は観客席。入り口もこの階にあり、バーが併設されている。つまり来場者は最上層から入り、階段で下へ降りていくという造りになっている。

出場者たちの控え室を覗いてみた。談笑している者もいれば、疲れて寝ている者もいた。ここ数日、サロンワークと並行してコンテストの準備に追われ、疲労困憊なのだという。体力自慢が多い美容師といえど、相当な負荷が体にかかっていたという証拠でもあった。
控え室をあとにして会場に戻る。18時前にはすでに満員だった。来場者たちはステージ手前に設置されたA(リアル)、B(クリエイティブ)の写真を、1つ1つ見て回っていた。「自分だったらどのように創作しただろうか」。それは絵描きが名作の前で立ち止まる姿と似ていた。もしかしたら嫉妬や羨望の思いで眺めていたのかもしれない。今日この場に招待された人たちは、各エリアで受賞(デザイナー賞・クリエイター賞・ギャラリー賞)した人たち。各エリアで共に戦ったライバルたちが来ているのだ。

18時ジャストにアワードが始まった。開会の言葉が述べられると、出場者とモデルがMCのコールとともに最上階から現れ、スポットライトを浴びながら、ステージへと降りていく。出場者のインタビューや昼間のコンテストの様子がスクリーンに映し出されると、会場から「おお」という低いどよめきが起こった。このあとは立食の懇親タイム。結果はそう簡単には発表されない。

このとき出場者に取材しようと近づくが、周辺に人が多すぎて進めない。だが、この光景がユニークだった。出場者が話している相手は審査員。モデルを間に挟んでしゃべっている。最初見たとき、ただ談笑をしているのかと思ったらそうじゃない。出場者が審査員を捕まえて、アドバイスをもらっているという構図なのだ。意見を求められたら答えるしかないわけで、ていねいに話す。するとその会話を聞こうと、観衆という名の美容師たちが集まってくる。そんなことがあちらこちらで起きるものだから、そこはある種、勉強会のようだった。

いよいよ結果発表のときを迎えた。スタリストとモデルが再び登壇し、一人ひとりの健闘を讃えて、ファイナリスト全員に記念のメダルが首にかけられた。そして、ライトが落とされ、ステージ中央にいるミルボンの佐藤社長に照明が集中した。そして優勝者の名前が読み上げられる。

「カーニバル、kazuさん」


その瞬間、kazuが膝から崩れ落ちた。今までクールな表情を崩さなかったモデルの顔がクシャクシャになった。歓喜というのは人間の理性を破壊する。kazuはうずくまったまましばらく立てず、体が小刻みに震えていた。肩を抱かれてようやく立ち上がり、涙をぬぐいながら優勝インタビューに答える。
「悔しい思いをたくさんしてきました」
本人のみが知る苦い過去ゆえの、しかし選びに選びぬいた彼ならではの言葉だった。
この後、ステージを降りてから、真っ先にオーナーのもとに行き、感謝の意を述べて抱きついた。


実は名前をコールされる直前、うつむきながら祈るように両手を握りしめていた者が、たった一人いた。
それがkazuだった。このコンテストに賭ける気迫と執念がDAオブザイヤーの栄冠をたぐり寄せたと言っても過言ではない。
こうして各地での戦いを含めた、約800人からなる半年間の闘いは幕を閉じた。
式が終わりkazuが控え室に戻ると、他の7組から拍手が起こった。先程までライバルだったもの同士がお互いを讃えあう美しい光景がそこにはあった。そしてその表情は皆、どこか晴ればれとしていた。自分印をしっかりと刻みつけた充実感があったのだろう。
やがて会場には誰もいなくなった。
祭りのあとの静けさは新しいヒーローを生み出した興奮と相まって、
心地いい余韻を残してくれた。

Photo : Koki Okumura
Text : Yasuhide Takizawa
Edit : Shingo Mine
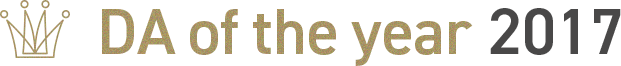


「儚さ」をテーマに、柔らかい質感や透明感を表現しました。モデルの肌の色と髪色を合わせたのがポイントです。